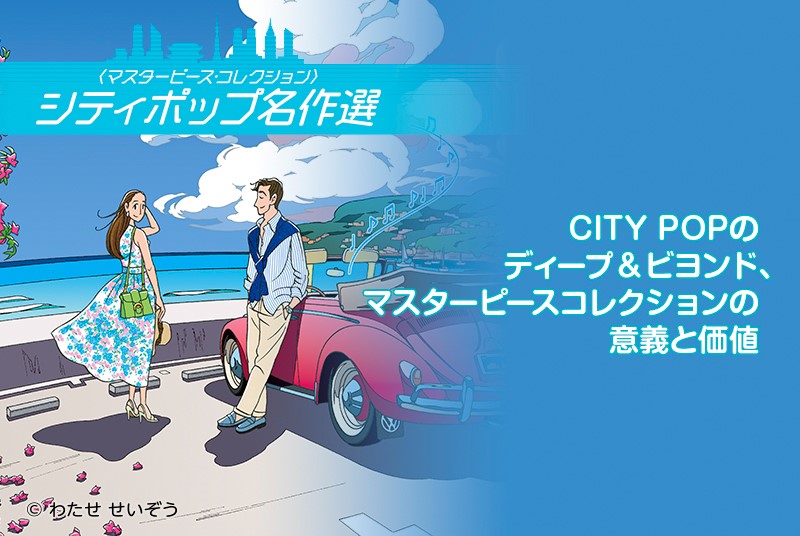
CiTY POP のディープ&ビヨンド、マスターピースコレクションの意義と価値
降って湧いたような世界的シティ・ポップの大ブームに乗って、7月・10月の2回に分けて34作品を復刻した『マスターピース・コレクション~CITY POP名作選』。そのシリーズの企画意義について、改めて検証したい。
そもそもの定義が曖昧なシティ・ポップであるが、おおよそのコンセンサスが取れるところでは、70〜80年代に流行った洋楽的かつ都会的感覚を持ったポップ・ミュージック、ということになるだろうか。歌謡曲や流行歌とは違った自作自演の楽曲は、当初ニュー・ミュージックと呼ばれたが、ギター1本で成立するようなフォークや攻撃的なロックは差別化され、洗練されたスタイルと上昇志向の社会的空気を反映させた明るい音楽性が好まれたのだ。
だがマスターピース・コレクションのラインナップを見てみると、CITY POP名作選という看板を掲げながら、少し違ったニュアンスが感じられる。杉真理&レッド・ストライプス、惣領泰則とジム・ロック・シンガーズなど、オリジナル・リリースが77〜78年のモノがあるのは当然ながら、ブレッド&バター、南佳孝、paris match、nananのアルバムなど、シティ・ポップの時代が遠く過ぎ去ったゼロ年代の作品群まで、広く構えてフォローしている。
その理由のひとつとして、2000年にビクター傘下でスタートしたaosis recordsの存在がある。標榜したのは、”大人による大人のための音楽”。70年代の米国でジャズのイージー・リスニング化を牽引したCTIを参考にして生まれたaosisには、多くのインストゥルメンタル奏者だけでなく、ベテラン・シンガーたちも籍を置いた。湘南サウンドでお馴染みの兄弟デュオ:ブレッド&バターは、その代表格。フォーク・グループ:赤い鳥やハイ・ファイ・セットで活躍した美声シンガー:山本潤子を中心としたカヴァー・ユニットnananもまた、それを投影させた。
対してaosisのコンセプトに則りながらも、ジャズ・ファンクやクラブ・ミュージック、ネオアコなど、若い感性で自分たちのスタイルを切り拓いたのがparis matchである。70〜80年代がシティ・ポップ全盛期なら、彼らは最早その次世代に当たるワケだが、今回のラインアップでは一番新しいユニットであり、現在のブームへの橋渡しをしながら今も活発に動き続けているのが頼もしい。
またシリーズ最多の4作品がエントリーされてる南佳孝も見逃せない。彼の作品群はaosis発ではないが、ブレッド&バター同様、シティ・ポップ黎明期から活躍するレジェンドのミレニアム・スタイルを伝えていた点で意義深く、時代に捕らわれず、ずーっと自分の美学、己の音楽性を貫いてきた姿に感銘を受ける。
aosis作品と共に発掘の現場になったるのが、invitationの作品だ。ポップス系アーティストを紹介するサブ・レーベルとして78年に創設され、かのサザンオールスターズもデビューからしばらくココに籍を置いた。時代を考えればシティ・ポップの流れを引くアーティスト/作品が多くなるのは当然だが、このタイミングでの創設となると、はっぴいえんど〜ティン・パン・アレイ〜ナイアガラのラインやサディスティック・ミカ・バンド系譜をシティ・ポップ黎明の中軸とすると、少しだけ後を追う形になっている。78年といえば、もうYMOデビューの年だからだ。でも日本の音楽シーン全体を俯瞰それば、謎は解ける。当時はまだアイドル歌謡がイケイケの時代。ビクター的に見ればピンク・レディーが人気のピークで、売れまくっていた時代だ。同時に新機軸としては、人気急上昇中だったジャズ・フュージョンに目を向けていた。
そのためinvitationは、大ヒットを出した後に再び頂点を目指すキャリア組、もしくは職人的アーティストや少し野心的な作品に寛容だった傾向がある。既に他の形でディグされ、リイシューされているアーティスト/作品も少なくないが、今シリーズでは高木麻早やリリィ、石黒ケイ、木戸やすひろ、黒住憲五、REICO などがこのタイプ。そこにJIVE、渕上祥人、それに故・村田和人と斎藤誠がによる覆面プロジェクト:21などのニュー・カマーが加わった。中でも黒住の移籍作『BOXING DAY』は、それまでのシティ・ポップ路線から一転、その頃の最先端テクノロジーであるサンプリング・マシンを駆使したバレアリック作。当時は理解不能で終わってしまったが、今こそ再評価すべき作品である。また21の2作目『GREETING』(新設されたRouxから発売)には、現在世界的注目を浴びる松原みき「真夜中のドア〜Stay with me」(80年のヒット曲)のメロウ・カヴァーがあるので要チェック。同曲のカヴァー・ヴァージョンがあまた溢れる昨今だからこそ、20年も前の斬新なアレンジに驚きを禁じ得ない。それを前にすると、若手アーティストによる最近のカヴァーの多くは、単に原曲の魅力に頼り切った工夫のないものと断言できる。
他にも、ベテラン移籍組の丸山圭子の2作、山本潤子を中心としたヴォーカル・グループ:APRIL、新人ユニットのボサノヴァ・カサノヴァやOPCELL、そしてコンピレーション『Voice Colors~あなたといたころ~』と、さすがはメジャー・レーベルならではのラインアップの豊かさ、幅広さ。しかもそれを通じて、シティ・ポップの表現の広さや深さ、音楽文化的存在感をも指し示している。志ある音楽家たちが丹念に創造したモノは、ただの売りモノやパッケージ商品ではなく、魂が込められた“作品”なのだ。
Text by 金澤寿和(音楽ライター / Light Mellow)
